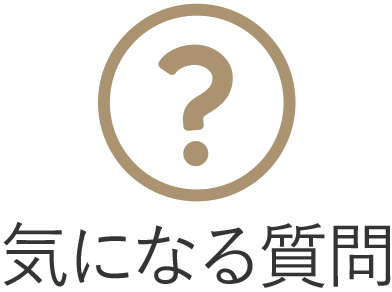松山医院大分腎臓内科での透析室における治療については、通信システムを導入し、患者さんの情報を一括管理しています。お一人おひとりの患者さんに対して、医師、看護師、臨床工学技士、理学療法士、診療放射線技師、管理栄養士、ドクターアシスタントクラーク(医師事務作業補助者)、看護助手が、多職種連携で、同じ情報を共有し、各々の専門性を活かして、患者さんに寄り添い、きめ細やかで質の高い透析治療を提供しております。
透析開始時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <1クール目>8:20より | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| <2クール目>13:45より | ● | – | ● | – | ● | – |
| <3クール目>17:00以降 | ● | – | ● | – | ● | – |
診療担当医 院長 松山 和弘
松山医院大分腎臓内科の
「人工透析」5つの特長
患者さんの状態に合わせた
テーラーメイド透析

当院では患者さんの腎臓の状態やライフスタイルに応じた透析医療を提供しており、血液透析・腹膜透析併用のご相談等も対応しております。日々多職種カンファレンスを行い、患者さんの検査データや他科の治療経過等の情報をチームで共有し、お一人おひとりに適した透析治療を提供できるよう協働しております。透析中も身近に看護師・臨床工学技士が配置されている体制を整えており、安心安全に治療を提供できるよう努めております。
テーラーメイド透析
ウルトラクリーンな透析水


ハイクオリティな透析治療を提供するにあたって、「水の清浄化」はとても重要です。当院は、自然に恵まれた環境であり地下約150mで自噴する地下水を逆浸透装置(RO装置)で清浄化して、透析液原水としています。通常であれば、このままでも透析液として十分使用できるレベルの水ですが、当院では、さらに透析室でRO装置を通して、ウルトラクリーンな透析液原水を透析液作成に用いて、患者さんの治療に使用しております。
清浄化レベルの高い透析液で透析すると、透析治療の効果がいいのはもちろん、肌の黒ずみや肌ツヤの劣化を抑える効果があると言われております。
透析水について
居住空間のような透析環境
当院の透析室は、居住空間と捉えて、
ご高齢の方にも優しい治療環境を目指しています

6床ごとの分離空調
暑がり・寒がりの方の対応が可能。天井の吹き出し口から床面への風流は患者さんに当たらないよう設計

静寂を保つ天井壁と間接照明
天井壁は静粛を保つよう吸音パネルを採用。照明は眩しくないよう間接照明

可動アーム型テレビ
各ベッドには、可動アーム型のテレビを取り付けております

感染対策用の個室
独立個室は4床ご用意。感染リスクの高い方の隔離的な治療を行っています

リクライニングベッド
リクライニングベッドは6床ご用意。腰痛をお持ちの患者さんにはこちらのベッドをご提案しています

美味しい食事の提供
季節を感じ、水や食材にこだわった、身体に良くて美味しい食事を提供

休憩ロビー
透析前後にお使いいただけます

休憩ロビー
お茶をご用意しております
透析中にストレッチや運動療法の実施


当院では患者さんのQOL向上を目的に、理学療法士が、医師の指導のもと、リハビリテーションの適応段階にある患者さんに対して、家庭での生活状況や、透析来院時における歩行動作状況を確認し、さらに、看護師、管理栄養士もまじえて、透析量や栄養状態など、総合的な評価のうえ、患者さんの個々に応じた運動強度を決定し、テーラーメイド的な運動療法を実施しています。頑固な腰痛症状など顕著な愁訴がある場合は、整形外科的治療を要す場合もあるため、専門医に対診のうえ、リハビリテーション指示をいただき実施しています。
最新透析装置を導入

オンラインHDF対応多用途
透析用監視装置DCS-200Si

オンラインHDF対応個人用
多用途透析装置DBB-200Si

オンラインHDF対応
多用途透析用監視装置DCS-100NX

当院では全台、最新のオンラインHDF対応患者監視装置を導入しています。透析通信システムは「Future Net Web+」を使用し、透析装置とコンピュータシステムを連携させることで、確実な情報伝達が行われ透析治療の安全性の向上を実現しています。
情報伝達の効率化によって、患者さんと接する時間に充てることができ、相談しやすい環境や小さな変化に気づけるよう細やかなサポートに繋げています。